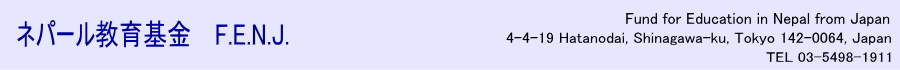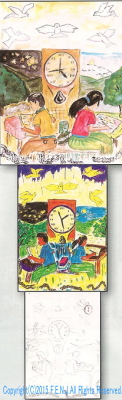左から: 有賀秋雄 : 近藤榮子 : 近藤かおり : サウスウィック シャノン かおり
◆私達がスタッフです◆
現在、私達は現地の学校、教職陣と一丸となってコンテスト、セレモニー、訪問展覧会を行えるように毎年活動しています。
近藤榮子は3か月、他のスタッフは約2週間の滞在中、絵画コンテストの1次審査/2次審査/3次審査、セレモニーと英語スピーチコンテストの準備、訪問展覧会で各学校を巡回する等の役割を担っています。
◆ごあいさつ/近藤榮子◆
1956年に史学科を卒業した立正大学は、仏教修行の壇林(大学)として400年前に創立され今ではかなりユニークな総合大学として注目されていますが、学びの精神的な支柱に仏教は存立しています。我がスタンスを仕立ててくれた母校と、年金を与えてくれる日本国、また健康な体を賦与してくれた両親、これら三要素に因ってこそネパールに20年継続して約3か月~6か月滞在し、子等と共にの年月を過ごせたのだと確認し直し、無事に「ネパールの子供たちの十年の足跡」を平成17年に刊行出来たことに新たな感謝の気持ちをお伝えします。
私が初めてルンビニを訪問した1997年(私のネパール行は1992年から)、母校立正大学史学科考古学部によるルンビニ発掘母体が進行中でした。しかも、その日「マヤ夫人が立たれお釈迦様がご誕生になった礎石」が発掘されていたのです。さらに、その時のチーフ、後輩の助教授(当時)上坂氏の配慮で入場不可の「釈迦誕生の礎石」のわきに降り立った時、私に託された”何か”を感じたのは私の幻覚でしょうか。
その導きで、平成17年(2005年)「ネパールの子供たちの十年の足跡」の出版に至ったのでは・・・。現在(2016年)85歳の私が60歳の昔でした。
「ネパールの子供たちの十年の足跡」の出版に際しては、日本語・英語・ネパール語の3か国語でと決めたのですが、日本在住16年のスーマン・ラジ・サルマ君、英語に堪能なラメシュ・プラダン氏など多くの助けが無ければ、全く不可能だったと思います。
現在のスタッフは、私の志を継いで毎年ネパールで活動を共にしてくれる私の娘のかおり、娘のパートナーの有賀秋雄氏、孫娘のシャノンと本当に嬉しい限りです。
私は、今年85歳(2016年現在)です。
5年前に娘が初めて活動参加の意思を現地で伝えると、私の続投が難しくなってもネパール教育基金は娘達、若いスタッフが継続してくれると知ると、教師陣を含めた参加者が続く将来を考えてくれるようになりました。
その後は、教師陣の積極的な参加型スタイルに移行してきています。
事前のミーティングでの役割分担やセレモニー終了後の反省会にも全校長と各学校代表教師が出席します。
ネパールの子供とネパール教育基金のことを考え、教師陣も私達と共に活気があります。
しかしながら、2015年4月25日にネパールを襲った大地震により2015年度のコンテストは中止せざるを得ませんでした。
本来ならば、すぐにでも駆けつけたい気持ちでしたが、手足の不自由な私が行ったところで余計な足手まといになってしまうと、ただただ現地の人々の無事を祈っておりました。
震災後から毎日、娘が電話で各学校の状況や安否確認をしてくれたことで多くの無事が確認できたことは本当に安堵致しました。
ネパールの震災前までは、2015年度のコンテストを終えてから、2005年~2015年の10年分を本にまとめ2冊目を出版する予定でしたが不可能となり、出版する代わりにその費用でネパール教育基金のホームページを立ち上げることにしました。
ペーパーレス化し、より多くの方に子供たちの絵を見ていただければと祈っております。
今後のコンテストの展開については、現地の視察からだと思っています。
視察は、2016年5月の予定です。まずは、各学校長、教師陣と直接会い、学校訪問をして何が必要かを見極めたいと考えています。
状況によっては、暫くはコンテストではなく何らかの支援策を考えることになるかもしれません。
これからもこのホームページを通してご報告させていただきます。
皆様には、言葉には表すことの出来ない感謝を、各ページにプラスして掲載させていただく事に致しました。 末永い御関心を願って。
近藤 榮子